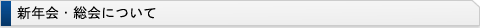 |
 |
平成20年度 理事会・総会・懇親会
|
 |
平成20年6月30日(月)ホテルセンチュリ−ハイアット東京におきまして、平成20年度 理事会・総会・懇親会が開催されました。
当日は多数のご来賓の皆様をお迎えし、当協会監事日米会話学院参与稲田脩先生の司会で、盛大に行われました。
参加者数は20校55名でした。 |
| 会長挨拶 |
 |
新宿区専修学校各種学校協会
会長 多 忠和 先生
みなさんこんにちは。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
募集の戦いもあと半分を残すだけとなりました。あと3ヵ月ほどで新しい学生募集・願書受付が始まる、こんな忙しい時に皆さんにおいで願いましてご足労お掛けしたと思っております。そう長い時間ではございませんので、非最後までお付き合いをいただきたいと思います。
私どものこの新専各の会員校のみならず、やはりこの厳しい専門学校の戦いの中で、どうやってやっていったら一番いいんだろうか、どういう方法がいいのかということで、あちらこちらで議論されております。その中でやっぱり大きいのは4年制大学との差別化や目標設定など教育の高度化というのが一番大きく取り上げられております。また、それぞれの学校の適性な自己点検、あるいは評価システム、それらの自校への導入等をしっかりやらなければならない時が来ているということです。専修学校関係者の間で議論をされておりますがいわゆる1条校化については、それによって専修学校の持ち味である柔軟性な教育ができないのではないかというようなご意見もいただいております。
高等学校からすると、学校の位置づけが学校教育法の1条かそうでないかは生徒や保護者には問題が無いわけで、「専門学校は高等教育機関である」と、そういう認識を持っておられます。現在高等学校の評価による教育の質の保証を責められておりまして、学校の種類は違うけれども「専門学校も第三者評価を行い、高等学校あるいは保護者に対し教育の質の保証を確保していかなければならない。」こんなふうに思っております。
専門学校は全国で現在70万人ぐらいの学生がいるわけです。専修学校に期待することは非常に大きくて、高等教育機関としての信頼性を確保してほしいと、それからまたどのような授業内容で資格取得等ができるのか、カリキュラムがどうなっているか、あるいはまた卒業後の就職など、学校の外見だけでなくて本当の意味でのそれぞれの学校の内容が知りたいというのが、高等学校の先生方からのご希望でありました。よく説明会、ガイダンスとかで、「うちの学校は創立何年です」、「校舎はこれくらいの校舎がいくつありまして」、「そんなことはもう聞きたくないんだ」、「分かっているんだ」、「そうじゃなくてそれぞれの学校の内容、中身を説明して欲しいんだ」と。「それがわからないと行っても何もならないんだ」、「それだけ聞くのであれば学校案内を見せてもらえれば十分だ」、「そうじゃなくてやっぱりそれぞれの学校が特色を持った部分」、あるいは、「絶対わしの所はここが強いんだ」、あるいは「こんな教育をしているんです」という「学校の中身を細かく聞きたいんだ」これが高等学校の先生方のご希望であります。
ですから今、学校説明会であるとか、体験入学であるとか盛んに行われている時期なので、そういう時期だからこそ、そういう機会に自分達の学校の授業内容であるとか、カリキュラムであるとかそういうことをしっかり説明してあげてほしいのです。そういうことを理解できないでただ見て帰ってしまうということであると、これは学生確保には全然何の役にも立たない。これは事実高等学校の先生から実際お聞きしたお話しですから間違いないと思っております。ですから皆さん方の学校にも、いろいろな学生達、あるいは高校の先生方が見学、体験入学、オープンキャンパス、そういう所にいらっしゃると思いますので、そういうところで是非やっていることの内容を大きくアピ−ルしてほしいんです。そうしますとやっぱり「あそうかこの学校はこういうところに特色があるのか」、「こういうところに就職できるのか」、「授業はこんな授業をやっているのか」、そういうことを学生、高校の学生に対してしっかり説明が出来るんだと、「今の状況だと説明できないよ」、「あそこの学校はもう初めてもう50年たつんだって」、「場所はここだよ、建物はこんだけあったよ」、そのくらいしか説明できない。これでは専門学校のみなさんに対して申し訳ないけど、内容がわからないんだから説明のしようがない。だから是非とも内容をしっかり説明して欲しいというのがご要望でございますので、皆様方もそれぞれそういうことを自分の学校に置き換えて、中身をしっかり説明してあげるということをやっていただきたいと思います。
また、専門学校は職業学校であると昔から言われて我々もその意識でやってきました。しかし、今や専門学校が職業学校なんだと、そう言って胸を張っていられる時代じゃないですね。大学がもう職業教育を始めているんですよ。自分達が持ってないものを色々なところから情報を得て、それで新しい職業教育ができるようなカリキュラムを組んでいるんですね。ですから「我々のところだけが職業学校である」、「専門学校は職業学校だから何の心配はないよ」、「俺の所さえ来ればいくらでも就職できるよ」今やそんな時代じゃないっていうことです。この大学全入時代を迎えて、それでなおかつ大学もただ学生を集めるだけではダメだと。だからいろいろなデータを見てわかりますように、やっぱり大学には入ったけれども出るところが無い。就職率がものすごく悪いんです。現実もやっぱり就職率は専門学校より劣っていますけれど、それをなんとかしようともの凄く努力しています。ですから我々も「専門学校は職業学校なんだから」「就職は俺たちに任せとけ」というだけでは済まなくなってきている。これからもっともっとそうなると思います。ですから大学のカリキュラムを見ても、今までみたいにただ研究であるとか、いわゆる一般論であるとか、ある一点に絞った教育の仕方とか、そういうことだけではなくて、こういう勉強をしたら、こういうことをやったら大学を卒業した時に、こういうところに就職できるよというような、職業教育を今もう始めています。ですから我々としては大学に比べれば非常に規模の小さい学校が多いわけですけれど、それはそれなりに今まで自分達で培ってきた伝統ある教育の仕方、そういうものをしっかり守った上に、また、大学ではできないもっと自由な教育の仕方があるわけで、自分達の学校のやり方で自由に物事を教えることができるわけです。ですからこういうこの自由な教育ができることを存分に生かして、専門学校のこれからをみなさんと共々一緒に守っていきたい。そんな風に思っています。新宿区は専門学校が一番多いんですね。62校ほどあるわけですよ。それで新専各に加盟くださっている学校が44校ですか、まだまだお入りになっていただける、加入していただける学校があると思いますので、そういう学校と連携を取りながら新専各がもっともっと伸びていけるよう、そんな協会にこれからも育てていきたいとそんなふうに思っています。
どうか、あともう数ヶ月にせまりましたけれども、今年の残り3ヶ月皆さんでそれぞれ頑張って、それで学生を確保するように努力してください。
以上でわたしの挨拶といたします。
多会長の挨拶に続き、稲田 脩監事の司会により、総会が行われ下記の議案が審議され、全員賛成により可決されました。
【議案】
第1号議案 平成19年度事業報告
第2号議案 平成19年度決算報告
第3号議案 平成20年度事業計画案
第4号議案 平成20年度予算案
第5号議案 役員改選 |
![]() |
| 東専各会長 小林先生挨拶 |
 |
東京都専修学校各種学校協会会長
日本福祉教育専門学校理事長
小林 光俊 先生
ご紹介をいただきました小林でございます。多先生およびこの新宿区専修学校各種学校協会にはわたくしも学校が数校ありまして、お世話になっています。
多先生にお話いただいたように、中込先生が東京都専修学校各種学校協会の会長を長らくお勤めいただきまして、現在、全国専修学校各種学校総連合会の会長をお勤めになっております。その後小泉先生に『東専各』の会長をお勤めいただいたわけであります、どうしても小泉先生が身を引きたいとこういうことでございました。それは定年制度を『東専各』の中で引いておりまして、その定年制度に引っかかるということで自らご辞退されたのでございます。その後を引き受けてくれということで、それぞれから声がかかってわたくしとしては、わたくしの学校自身も今大変厳しい状況でありまして、正直言ってリストラもお願いしなきゃいけないということ、学校の再編成も進めなければならない状況にあるわけでございまして、そういう厳しい中で自分の頭の上のハエを追えない状況なのに、『東専各』の会長が務まるんだろうかと、何回もご辞退申し上げてきたわけですけれども、しかし厳しい状況はどこの学校を見ても同じで、どうしてもここは引き受けてほしいということで、受けざるを得ないということで『東専各』の会長を分不相応でありますがお引き受けさせていただいたのでございます。
何にしても出身母体はこの『新専各』でございます。『新専各』の皆様方の力を借りて、『東専各』、そして今は『全専各』の会長も『新専各』から出ているわけでありますので、いずれにしても力を合わせて職業教育の振興に、声を大にして実現していかなければならないと思います。
多先生が先程からお話していただきましたが、専門学校の教育の中身が、更に充実をして職業教育が日本国内で重要な位置を占めていることを、行政当局や政治家の皆さんにも理解をいただいて、職業教育の振興発展を取られるような政策に切り替えていただかなければいけない。と思うわけです。特に日本は戦後、ずっと高度成長を通じ発展をしてきたが、この20年間は大変厳しい状況で、バブルがはじけて以降は教育予算もずっと削られている状況です。
わたくしは、多先生もおしゃいましたが、日本国は資源が殆んど無い。人材しか資源が無いわけですから、この人材の養成、それも職業教育の養成、高度な専門教育の充実を、成し遂げて、日本はかつて経済成長を遂げたわけですから、ここはもう一回、アジアの国のリーダーとして職業教育をきちっと位置づけをし、世界の各国から日本へ職業教育を学びに来る、専門教育を学びに来るという、若者を集る。さらに日本の職業教育制度の発展が世界のリーダー、人材養成のモデルとしてつなげていくという、政策を国を挙げて取るべきでわないかと、思っているわけです。地方のあまり必要の無いところに立派な道路を作るということもいきすぎてもいけません。あるいは、必要の無いダムを40年、50年も前に計画したものを今は、必要性が無くなっているにもかかわらず作る、膨大なそういう予算を削減して、教育、人材育成に予算をさくべきだろうと思っています。OECDの調査によれば日本の教育予算はGDP費3.5%に減っているわけです。ここ20年間で、がた減りしたわけです。以前は、GDP費5%〜6%多いときは10%も占めてたわけです教育予算として。今や3.5%だからOECD主要加盟国の中の後ろから数えて早い方です。主要先進国27ヶ国の中で26番目ということで、大変に厳しい状況になっているわけです。OECD加盟国の平均はGDP(国民総生産)に対する、国が支出する教育予算の平均は5%です、平均が5%。日本は3.5%で1.5%低いんです。
日本は資源が無くて、人材育成をしなきゃいけない、状況にあるにもかかわらず、国民総生産比でいえば、今言いましたように27カ国の主要先進国の中で日本は後ろから2番目、それだけ今教育予算が削られている。必要の無い道路を作ったり、あるいはダムを作ったりそういうことに使う金よりも、人材育成に金を使うということを、認識をしていただく、こととを政府および政治家に理解していただくように働きかけていかなければならない。そしてこの国を人材立国にして、職業教育を振興させていくことを、その実現を図ることが必要と思っています。
一条校化ということも今『全専各』では進めておりますが、東京、特に新宿から『全専各』の会長を送り出しているわけでありますから、その責任も感じているところであります。これにはそういうことをして何が得になるのか、はっきりわからないという不安が会員の皆様にもおありであろうと思うんですが、要するに専修学校は後から出来てきて、今から33年前に私学助成金と共通一次テスト、専修学校制度と同時に永井道雄文部大臣の元で生まれて、33年経ってきたわけですね。私学助成金がその後ずっと発展をして、今や3,200億ぐらいが大学を中心に配られているわけでありますけれども、しかしこの私学助成金だって、ここ20年間増えていない状況です。ところが先ほど多先生がおっしゃっていましたが大学の数および大学生はこの20年間で2倍になっているんです。そうすると私学助成金は増えていないわけですから、わたくしが塩川正十郎さんと今年の初めある会合で一緒になった時、こうおっしゃっている「私は今から20年程前に文部大臣をやっていた。その時の私学助成金3,400億だった今は3,200億その時よりも大学生は2倍に増えています。そうすると学生1人あたり1/2になっているということなんです。」ですから大学の方も大変だろうと思うわけです。良い教育をするって言ったってその予算が無いわけですね、1/2ですから学生の数だけ増やすというのはどうかと思うんですが。東京都は大学に関する進学率は53%以上です。これでは、ほとんどが大学へ行っているという状況ですから、先進国どこをみても大学教育を30%以上を越している国はあまりないんです。エリ−トというのはそんなに沢山いるわけではありませんから、大学1/3そして、職業教育1/3、その他1/3ぐらいのバランスが一番教育体系としていいんだろうと思うんです。大学に行く必要の無い人が大学へ行って、フリーターやあるいはニートになる。目標がわからなくて、あるいは勉強についていけなくて、そういう状況ではおかしいと思います。ある会合でも大学の先生が嘆いておりました、大学の補習授業で中学校2年の数学教科書と理科教科書を、補習授業と称してやっている。そういう状況の大学もあるいうことでありますから、何をかいわんやです。すなわち大学教育が大学教育になっていないということなんです。そういう人たちがフリーターになったり、あるいは卒業しても就職できなかったりする人たちがいっぱいいる。それよりも専門学校、専修学校に来て職業教育をきちっと学んでいただいて、そして社会に出てその技術なり、知識を生かしていただくということを、奨励していく。これはヨーロッパなどはできているんです。ですから是非日本もそういうふうにして、バランスのある教育体系を作っていくべきと思う。それを声に出して政治家なり、行政、政府に迫っていく必要があるんだと思っております。新宿区の皆様方の力をお借りしていろんなことが実現できるように、努力をしていきたいと思いますのでよろしくご協力の程お願い申し上げます。
|
 |
|
![]() |
| 懇親会 |
| |
総会に続き、場所を移し懇親会が行われました。
懇親会は、多数のご来賓の方々にもご出席いただき、盛大に行われました。
|
| |
【ご来賓】
| 新宿区 |
総務部 |
|
総務部長 |
野口 則行 |
様 |
| 新宿区 |
教育委員会 |
教育政策課 |
地域家庭教育係長 |
榎本 実 |
様 |
| 新宿区 |
地域文化部 |
文化観光国際課 |
課長補佐 |
石川 嘉則 |
様 |
| 新宿区 |
地域文化部 |
文化観光国際課 |
主事 |
笠原 崇 |
様 |
| 新宿区 |
子ども家庭部 |
子ども家庭課 |
活動支援係長 |
菊池 恵子 |
様 |
| 新宿区 |
子ども家庭部 |
子ども家庭課 |
活動支援係 |
勝木 智一 |
様 |
| 新宿区 |
総務部 総務課 総務係 |
主事 |
原田 由紀 |
様 |
| 東京商工会議所 |
新宿支部 |
事務局長 |
鈴木 秀昭 |
様 |
| 株式会社専門学校新聞社 |
代表取締役 |
西島 芳男 |
様 |
| 株式会社専門学校新聞社 |
営業企画部長 |
内藤 達實 |
様 |
| 株式会社新宿区新聞社 |
部長 |
岡本 高司 |
様 |
|
|
| |
![]() |
| 来賓挨拶 |
 |
新宿区総務部総務部長
野口 則行 様
ただ今ご紹介いただきました、新宿区総務部長の野口でございます。
常日ごろ新宿区の行政に皆様にはご理解、ご協力いただきまして、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。
昨年は、新宿区におきましては新しい基本構想を作りまして『新宿力』で創造する、にぎわいとやすらぎのまちというキャッチフレ−ズで、今行政を積極的に進めているところでございます。この『新宿力』というひとつの要素としてはやはり新宿区の持つ多様性だというふうに思います。そのことはですね、30万区民だけで無くてですね、80万の昼間人口、それから新宿区の駅では乗降客が350万人と言われております。まさに新宿区は交流の拠点であります。特にこの若者の交流の点でいえば皆様の専修学校、各種学校の活動というのはその大きな支えになっているんだろうと思います。そういう意味では生涯学習の場、区民を初めとした新宿区に多くいらっしゃる方々の場の提供ということと交流の活力の源泉だろうというふうに思っています。特に昨年は学校教育法も改正されてですね、各学校も自己評価をしてそれを公表するということが求められるようになりました。そういう中ではこの新宿区の専修学校各種学校の皆様はですね、NPOの立ち上げなど率先して取り組まれて、第三者評価なども取り組まれているということなどもお聞きしております。そういう意味では交流の拠点であると同時に、これからの多様化した、高度化したですねやはり教育の場という点でもですね皆様の活動がこれからも社会にとって、新宿区にとってもですね、大変重要になってきますので、これからの皆様方の旧に増してのですね、ご尽力を心からいただきたいというふうにお願いを申し上げます。結びになりますけれども、専修学校、各種学校、新宿区の協会の参加の学校の益々のご発展と皆様のご健勝をご祈念申し上げまして大変簡単でございますが、挨拶とさせていただきます。
本日は区長が所要によりまして出席できませんで、わたくし代理で挨拶させていただきました。大変申し訳ございませんでした。お招きありがとうございました。 |
| |
![]() |
| 乾杯 |
 |
新宿調理師専門学校理事長
関川 惠一 先生
ただ今ご紹介いただきました、新宿調理師専門学校 関川と申します。本来、会長さんが挨拶してその後にと思ったんですけれども、何かすぐに乾杯、今日は東京都の専門学校野球大会の決勝戦がありまして、わたくしそこの会長をしておりますので、その決勝戦の会場から直接来たんですけれども、新宿区の専門学校の副会長に今回なってくれいうこともあってですね、わたくし断れない人が一人、日本電子の多先生いわばこの野球を立ち上げてわたしを会長にしていただいたのは日本電子のおかげですので、多先生からお前やれ言われると、もう断ることができないと、まず来るには、まずたくさんの人を呼ばなきゃいけないということで、今日は広報部を3人連れて4人で参加することにいたしました。ますますの発展を祈念いたしまして 乾杯。
|
![]() |
| 留学生奨学金について |
 |
新宿区 地域文化部 文化観光国際課
主事 笠原 崇 様
皆さんこんばんは。新宿区地域文化部文化観光国際課の笠原と申します。この場をお借りしまして、外国人留学生の学習奨励基金について、少しご説明させていただきたいと思います。この外国人留学生学習奨励基金というのは、過去にお二人の方からいただいた寄付を基金として運用することで、奨学金を支給するものです。平成4年の事業開始から現在に至るまでに200名を超える外国人留学生の方に年額240,000円を支給しております。
新宿区で勉学に励まれる外国人留学生の方は年々増えております。現在の状況で言いますと、新宿区に外国人登録している留学生の人数は約5,000人です。新宿区には現在約32,000人の外国人が暮らしていますが、その中でも留学生の方が非常に多くいらっしゃいます。また、約4,000人の就学生を合わせて考えると約9,000名となり、新宿区に外国人登録をしている方の約30%が、勉学に励まれている方ということになります。留学生の方はアルバイトにかなりの時間を費やす傾向があるとお聞きしています。奨学金を支給することで勉学に励まれている留学生たちの経済的負担を軽減できればと思っております。専修学校各種学校協会を通しまして、専門学校に通う留学生に奨学金の申請をしていただいておりますが、まず、このような新宿区の主旨というものを理解した上で申請していただければとてもありがたいと思いますので、今後とも是非よろしくお願いいたします。
|
| |
| 文部科学省委託訓練事業について |
 |
新宿区 子ども家庭部 子ども家庭課
活動支援係長 菊池 恵子 様
皆さんこんばんは。新宿区子ども家庭部子ども家庭課活動支援係 菊池と申します。どうかよろしくお願い申し上げます。
先ほど、総会の中で「若年層キャリア育成プラン:職業体験&職場見学講座」事業のご紹介があったかと思いますが、17年度にも新宿区教育委員会と新宿区近隣の専門学校の方々が連携して、区内の中学生を対象に職業体験事業を実施されたと聞いております。
今年度、区では組織改正があり、青年層のキャリア教育に取り組む事業ということで新たに子ども家庭課において、専門学校の皆さんと一緒に連携して事業を実施してまいりたいと思います。
どうか、ご協力、ご参加いただきますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。
|
| |
![]() |
| 懇親会 |
| |
【初参加の先生方】
| 新宿調理師専門学校 |
岡田 典子 |
先生 |
| 新宿調理師専門学校 |
小嶋 芳光 |
先生 |
| 東京外語専門学校 |
梶原 康平 |
先生 |
| 東京国際福祉専門学校 |
菊地 強 |
先生 |
| 東京製菓学校 |
中村 勇 |
先生 |
| 目白デザイン専門学校 |
村川 美喜子 |
先生 |
| 新宿日本語学校 |
江副 隆秀 |
先生 |
|
|
| |
  |
 |
![]() |
| 中締め |
 |
早稲田美容専門学校校長
小倉 規布佳 先生
宴たけなわではございましたが、小倉先生の掛け声のもと『一本締め』で会を中締めいたしました。
|
 |
|
|
|
|
|
| 17年度新年会・総会はこちら>> |
| |
